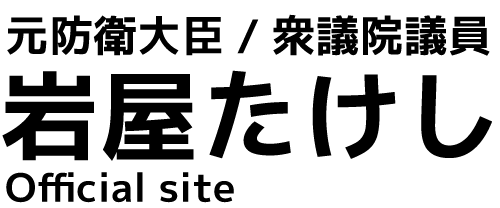忙中閑話「アイヒシュテット」
ドイツはバイエルン州の州都とも言うべき工業都市ミュンヘン。そのミュンヘンから電車で北に向かって一時間半足らず行き、さらに支線に乗り換えて10分ほどで着くところが、長女がこの春から一年間の予定で滞在しているアイヒシュテットという町である。
この夏、家族を連れてそこへ娘の様子を見に行くことにした。最初は家内と二人のつもりだったのだが、途中から次女がどうしても連れて行けというので、結果、三人の旅となり、しからばこの際は現地の長女も同行して一緒に周辺国を回ってみようということになって徐々に計画が膨らんでいった。
いまどきはネットで航空券からホテルかツアーに至るまで簡単に予約することができる。自分はいつも秘書任せでやったことはないが、次女がその方面に堪能で、「人数が増えたのだから、とにかく格安にあげるように」という家内の強い指示のもとに奮闘し、ほどなくして約一週間の旅程ができあがった。旅の最大の目的は「アイヒシュテット訪問」であるから、着いた翌日にその予定を組み入れてある。
空港に迎えに来ていた長女は拍子抜けするくらいにドイツへ出発する前と変わりなかった。まぁ、行って半年に満たないのだから当然かもしれぬ。離れて半年ばかりなのに小生は人目もはばからず長女に駆け寄りハグをした。家内と次女は知らん顔。当の長女も迷惑そうな顔。女というものはやはり冷たい生き物なのか。。。
翌朝、いよいよアイヒシュテットに向け出発である。ホテルを出てミュンヘン駅まで徒歩5分。長女が何の交通機関に乗っても乗り放題だという「バイエルンチケット」なるものを購入してくれていた。列車が町の郊外に達すると、窓の外に一面の畑が広がる。そこから先はどこまで行っても同じ風景が続いていく。田舎町だとは聞いていたが、この調子で走り続ければとんでもない辺地に辿り着くのではないかと娘の顔を横目に見ながら僕はいささか当惑し始めた。
家内は今回の度に際してスーツケースの半分を占めるくらいの食料品や衣料やお菓子類を娘のために持参していた。「そんなもん、ドイツだって買えるだろうに。送ったっていいし」と言ったのだが、どうしても「持っていく」と言ってきかない。まぁ、それも母心だろうと観念して重たい荷物をひきずっていくことになったのだが、日本を出発する際に、案の定、重量がオーバーしていて余分に料金をとられるはめとなった。
アイヒシュテットの無人駅を降り、その重たいトランクを引きずりながら僕と家内、長女と次女の四人連れで町のはずれから路地をとぼとぼと入って行くと、意外なことに目の前に中世の名残りを感ずる風情ある街並みが広がってきた。そこそこに商店なども居並び、途中、観光客らしき人たちとも行き交ったりしたので、「ああ、それほど寂しい町でもなさそうだな」と僕は少しばかり安堵した。
長女に留学を勧めたのは自分である。学生時代、留学しなかったことをすこぶる後悔していたので、子どもたちには「たとえ短期でもいいから海外に暮らして世界を見てこい」と口を酸っぱくして言い続けてきた。長女は素直にそれに従った。自ら大学の姉妹校を見つけてきて、知らない間に考査を受けて合格し、「私、行ってみることにしたよ」と報告してきた時には本当に嬉しく思ったものだ。
「で、どこにあるんだ?その学校は?」と聞くと「アイヒシュテット」だという。「ちょっと待て。パパが調べてみるから」と地図を開いて探したものの、いくら睨みまわしてみてもそんな町の名は地図上にはない。「ずいぶん田舎町なんだな?きっと」と訊くと、「うん。行ったことある先輩がそう言ってた」と言う。
「そんな田舎町でお前、大丈夫か?」「うん。電車でミュンヘンにも遊びに行けるみたいだし」。。。留学とはいえ、東京のど真ん中の学校からそんな辺鄙なところに行かせるのはちょっと可哀想かもしらんという思いが一瞬、頭をよぎったが、もう決めてしまった以上は仕方がない。「パパも都合がついたら一度行ってみてやるよ」と言ったのが、今回の旅につながったというわけだ。
駅から歩いて10分もしないうちに娘のアパートに辿り着いた。階段をウンショウンショと重い荷物を持ち上げながら三階まで上がると小さなドアの前に出た。娘が鍵をあけて中に入ると日本で言えば6畳間くらいの小さな部屋がふたつ並んでいる。ドイツ人の学生と相部屋だと聞いていたが、今は夏休みで帰省中だという。道すがら「挨拶してお茶か食事にでも誘うべきだろうか・・・」などとあれこれ考えていたのだが、相手がいないのでは仕方がない。
共用の小さなキッチンとシャワーだけのバスルーム。箪笥や押し入れなどもなく、部屋の隅をカーテンで仕切った中に衣類などがたたまれて置かれていた。机と本棚の前には大きな一枚窓。開放すると気持ちよさそうだったが、網戸がついてないので虫が舞い込んでくるらしくあまり開けないそうだ。本棚には家内が日本から送った本が10冊ほど並んでいた。家ではあまり本を読んでいるのを見たことがなかったが、こちらへ来てからはよく読むようになったのだと言う。おそらく時間をもてあましているのだろう。
長女はおとなしい子だ。親が言うのもなんだが、極めて温厚で優しい性格である。激しくものを言うのを聞いたことがない。彼女は幼児の頃からひどいアトピーに悩まされてきた。お陰で今はほとんどといっていいほど改善しているが、そんな体験が娘を少しばかり引っ込み思案な性格にしているのではないかと、そのことがずっと不憫に思えてならないできた。だから、留学が決まった時、当初の嬉しい気持ちとは裏腹に徐々に心配のほうが大きくふくらんできたのだ。「水は合うのだろうか。食事は大丈夫か。友達は作れるのだろうか。ホームシックになりはしないだろうか・・・」。
親馬鹿と言われればそうかもしらん。「子離れしてない」ときっと笑われるに違いない。離れていけと言った自分が、いざ離れていかれると寂しくて仕方がない。たくましくなれと言った自分がその実は心配ばかりしている。僕は娘が寝起きしているベッドに腰掛け、小さな部屋の隅々に目をやって果たして不自由がないだろうかと点検した。そして、どうかこの子がこの一年を寂しがることなく健康でのびのびと過ごして欲しいと心から願った。
アイヒシュテット訪問を済ませた僕らはミュンヘンへと戻り、その後、数日間にわたってザルツブルグ、ウィーン、プラハへの旅を満喫した。バスルームといってもシャワーしかついていないような安ホテルを泊まり歩き、移動は重い荷物をひきずりながらすべて公共交通機関で済ませるという旅だったが、その分、みんなが力を合わせて旅を成し遂げたという観があって、とても思い出に残る家族旅行になったのではないかと感じている。
いよいよ帰路に着く日、娘が空港まで送りにきた。家内と次女はお土産を買うのに忙しくしていたが、小生は朝からなんとなく気が落ち着かない。このまま長女を連れて帰りたい気分だったが、そうもいかない。チェックインの手続きが終わり、ゲートに向かう前にもう一度、長女にハグをしたら、不覚にも目がうるんだ。幸い、家内と次女は知ってか知らずか、あらぬ方向を見ていてくれたが。
「じゃぁね。元気で頑張るんだぞ。いろんなことを積極的にやってみるんだぞ」。声が震えないようにそう言ってゲートをくぐり振り返ったら、既にきびすを返して出口へと歩いていく娘の後姿が見えた。凛としているような寂しげなような。。。僕はその娘の姿が見えなくなるまでそこに立ち止まって見送った。