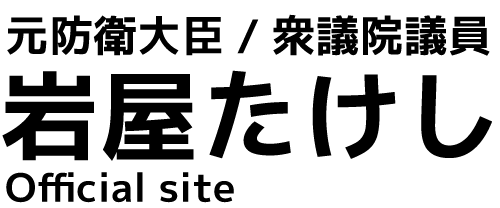忙中閑話「獄中記」
以前に家の改築をやっていると書いた。お蔭で作業は順調に進んでいるが、実は古い家を取り壊す際に我が家にとって実に驚くべき資料が発見されたのである。それは他ならぬわが祖父、岩屋護の「獄中記」である。
昔、祖父がかかわったそんな事件があったとは聞いてはいたが、まさかその記録が残っていようとは思いもよらなかった。初めてそのボロボロの大学ノートを手にした私は夢中でむさぼり読んだ。そして、祖父の思いが手に取るように伝わってきて涙した。「獄中記」などというと、そうか、あいつの爺さんはそんな悪党だったのか!という声が早速に聞こえてきそうだが、決してそうではない。以下、その顛末を記す。
私の祖父は大分県は直入町長湯という片田舎の温泉町の出身である。子どものころ、勉強はよくできたらしいが曽祖父が酒飲みでなおかつ博打打ちだったらしく(これらは祖父からの伝聞による)、上級の学校へは行かせてもらえなかったという。このまま田舎に残ったのでは男子としての志を果たせぬ、と考えた祖父は半ば家出同然に当時、活況を呈しつつあった別府市に夢を抱いて出てきたのであった。山奥の育ちであった祖父はそれまで海を見たことがない。別府に着いてはじめてやったことは何かと言えば海岸まで行って海の水を舐めてみることであった。「ああ、本当に海の水はしょっぱい!」というのが別府の第一印象だったという。
幼い妹を連れて別府へ出てきた岩屋少年の最初の仕事は図書館の小間使いである。なぜ、そんなところへ職を求めたのかと自分が小さい頃、祖父に聞いたことがあったが、答えは「そこへ行けばタダで本が読めたからだ」とのことであった。自分よりできの悪いやつが学校に通っている姿を田んぼから悔し涙で見つめていた、と祖父はポツリと言ったことがある。その悔しさがバネになったのだろう。本を買う金の無い祖父が勉強するにはそれしか方法がなかったのだと思う。仕事が終わると図書館に居残り、そこにある本をかたっぱしから読んだそうだ。
そこで「独学」を終えた祖父は地元の小さなローカル紙に勤めることになり、新聞記者としての生活をスタートさせる。そこで腕を磨いたあと、ほどなく独立し、現在まで続いている「今日新聞社」を起こした。そういう経歴からすると当然のこととも言えるが、祖父は実に筆まめな人だった(だからこそ本タイトルにある「獄中記」まで丁寧に残すことになるのだが。) 新聞社はその後、言論統制かなんかで一度廃刊になり、のちに当時の部下の方によって復刊されて現在に至るのだが、祖父のほうは新聞社をやめたあと、(今では信じがたい人事と言えるが)突如、別府市の衛生課長として市に奉職することになる。
役所で持ち前のバイタリティーと行動力を発揮した祖父はあれよあれよという間に出世を果たし、45歳の若さで当時三人いた助役の一人に抜擢された。そのときに別府市の新規事業として「競輪事業」をスタートさせる仕事を受け持つことになる。「別府競輪」の担当助役、正確には「競輪開催執務委員長」という役である。しかし、この任に就いたことがのちの大疑獄事件に巻き込まれていく発端となるのである。
昭和25年7月19日、(もちろんこのときは小生の姿も形も無いわけだが)、大分地検は別府競輪をめぐる背任横領、贈収賄容疑で市の助役室や祖父の自宅(先般、解体したばかりの我が家である)等の家宅捜索を行ない、重要書類を押収すると同時に祖父ら関係者を収容した。収容されたというと聞こえがいいが、要は「逮捕された」のである。祖父の容疑は別府競輪株式会社創設時に各種の便宜をはかったことで当時の金で百万円を収賄したということであった。
収監された直後、祖父はそのときの心境をこう語っている。
「私に少しもやましいところはない。なぜこうなったのか、取調べの根拠がわからぬ。疑いの筋をはっきり知りたい。一身上の問題は別として一般が市政に対して持っている不明朗なものを一刻も早く取り除くために公正迅速な取調べを進めていただきたい。」
田舎から出てきて学問も無くひたすら自力独行でのしあがってきた祖父にとって、突然身にふりかかってきた嫌疑、そして思いもよらぬ逮捕の衝撃はいかばかりだったかと思う。やっと築き上げてきた人生のすべてを無にしてしまうほどの大事件である。祖母や、まだ医学部の学生だった父にとっても悪夢としか言いようのないできごとだったに違いない。しかし、捜査はその後も急ピッチで進展し、競輪会社の社長はじめ幹部諸氏、さらには市議会の関係議員も次々に逮捕されてまさに一大疑獄事件へと発展していく。世間は誰しもが「岩屋はクロ」と思い始めていた。しかし、そこから祖父の一世一代をかけた壮絶な戦いが始まるのである。
市の助役まで登りつめたとはいえ、こと刑法関係の知識など希薄であったはずの祖父は獄中でこれから始まる戦いへ備えての猛勉強を開始する。来る日も来る日も法律書や判例集を差し入れさせてはかたっぱしから読破し、弁護士と打ち合わせ、着々と理論構築をしていった。のちの公判の際には裁判長も検事も舌を巻くほどの理路整然たる弁舌を駆使したというから実に恐るべき頑張りである。ファイトと押しの強さでは誰にも負けなかったという祖父の真骨頂が獄中においてあますところなく発揮されたわけである 。
既に手垢にまみれ、ボロボロになっている「獄中記」をめくると、表紙の裏にこんな詩が書かれてある。
「わが道は冷たき道ぞ 石をもて 打たれたりとも この道をゆく」
「戦いは男のゆえぞ われはゆく 妨ぐものは 踏み潰しつつ」