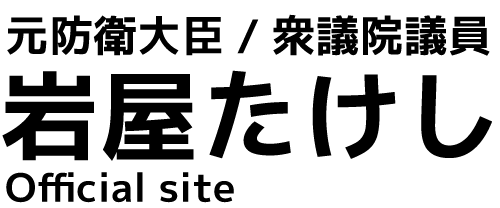忙中閑話「薩摩」
NHK大河ドラマの「篤姫」には毎回、泣かされた。番組が始まった当初は、「歴史考証に問題がある」だの、「家族に焦点を当てたストーリー展開になっているが、果たしてその時代、宮中や大奥にそんな意識があったのか」などとずいぶん酷評されたものだが、出演者たちの熱演もあってか、次第に人気を上げ、終わってみれば、歴代の大河ドラマの中にあっても長く人々の記憶に残る名作品となったと言っていい。
なぜ、これを見て小生が泣いてしまうのかをと言えば、まず何と言っても、篤姫の郷里たる薩摩のシンボル、「桜島」が毎回、姿を見せるからだ。多感な高校時代を鹿児島の地で過ごした小生にとっては、桜島はまさに青春のシンボルでもある。桜島の雄姿を見ながら過ごした三年間はわが生涯においても最も濃密な時間であった。それがゆえにその雄姿に触れるだけで、中身を観る前段階で思わず感情が高ぶってしまうのだ。
父に連れられて高校受験に行った時、初めて目の前に桜島を見て、その雄大な姿に感動したことを今でも思い出す。大分県と言えば、お隣の阿蘇に巨大な噴火口を見ることができるものの、鹿児島市内を悠然と見下ろす形で錦江湾に聳え立つ桜島の発する噴煙はそれまでに見たことのないものだった。むろん写真で見たことはある。しかし、実物の迫力はそれとはまったく違うものだった。「ああ、これが薩摩を象徴する風景なのか」と感嘆したものだ。
その初めての桜島との邂逅は本当は一度きりで終わるはずだった。なにしろ、試験がまったくできなかったのだ。それもそのはず。小生、地元の中学校ではそこそこの成績だったものの、学校の教科書でしか勉強したことはなく、塾なども行ったことがない。見たことも解いたこともないような難問の洪水に打ちひしがれた試験だったので、まさか合格するわけがないとあきらめていた。だから、父と鹿児島をあとにする時は「せめてこの風景を目に焼き付けて帰ろう」と思っていたのだ。
父も落胆した息子の様子を見て察したのだろう。「この際は鹿児島見物でもして帰るか」と一日余分に費やしてくれた。父は昔の鹿児島医学専門学校、現在の鹿児島大学医学部の出身だったので、土地勘があるのだ。あちこち連れまわしてくれて、「ほら、ここが島津の殿様がいた別荘だ」とか、「ここで西郷さんが最後を遂げたのだ」という風に、歴史考証を交え、時折、学生時代に覚えた鹿児島弁を織り交ぜながら観光案内をしてくれた。もう「時効」だから言うが、その日の晩には父の昔のガールフレンドと一緒に会食をするというおまけまでつけ加わった。
しかし、「まぐれ」というものはあるものだ。合格発表のその日、とうにあきらめていた小生は二階の自分の部屋で布団をかぶって寝ていたのだが、階段を駆け上がってきた母の慌てた声でたたき起こされた。「たけっさん、たけっさん、あなた、合格したのよ。合格だってよ!」
以来、毎日、桜島を眺めながらの三年間が始まった。初めて親元を離れたのがやはり寂しくて、最初の連休は別府にすっ飛んで帰ったものだが、次第にホームシックからも解放され、休みになると鹿児島に居残って友人たちと「天文館」という繁華街に遊んだり、市内にある名所旧跡を訪ね歩いたりした。受験の時に父が連れて行ってくれた「城山」にも行ってみたし、磯の島津別邸にも行った。西郷さんと大久保さんが幼い頃を過ごした加治屋町というところにも立ち寄ってみたが、とにかく何処へ行っても、誰と話しても、「薩摩」という旧藩の残影が色濃く残っていることには新鮮な驚きを覚えたものだ。
我が郷里、別府はその昔、「天領」だった。いまの大分県の大半はその頃「豊後」と呼ばれていたのだが、江戸の後期には幾多の小藩に分立していて、薩摩のような雄藩があったわけではない。それがゆえか、大分の県民性は今でも「赤ネコ根性」と言って、なかなかまとまりにくいのが特徴だとされている。戦国時代には、キリシタン大名として有名だった大友宗麟という殿様がいて、南蛮貿易を盛んに行ない、積極的に西洋文化を取り入れた。それがゆえに「豊後」は文化面での先進性は持っていたのだとは思うが、総大将たる宗麟は残念ながら「戦国大名」としてはB級だったと言わざるをえず、それこそ「薩摩」と戦って敗れるなどしてやがて没落し、その後、領地が切り刻まれることになったわけだ。したがって、幕末から明治維新にかけての日本の激動期に「豊後」ゆかりの名が登場することはほとんどない。敢えて言えば、啓蒙思想家として名を馳せた福沢諭吉くらいだろうが、この人は正確に言えばお隣の「豊前」の人である。
ところが、鹿児島へ行くと、何処へ行っても「薩摩」、「薩摩」、だ。いまだに県名を「薩摩」というのではないかと思えるほどであって、「近代日本を作り上げたのは薩摩だ」という矜持が人々に共有されているように感じられる。理想の男は言うまでもなく「西郷隆盛」。みんな、「せごどん(西郷さん)」、「せごどん」と、いまなお翁が生きているかのような呼び方をする。鹿児島出身の同僚は「薩摩隼人」と言われるとずいぶんと誇りをくすぐられるようで、「エヘン」といった顔をするのだが、小さき天領出身の小生にはそれが正直、うらやましかった。
その鹿児島での学生時代、「大久保利通」の銅像を作るべきかどうかということを巡って、県民の間で大議論が展開されたのを覚えている。「へぇ、大久保さんの銅像は今までなかったのか」と門外漢には不思議に思えたのだが、「せごどん」を結果として死に追いやった「一蔵」については、おそらく県民感情の中に複雑なものがあったのだろう。もちろん、近代日本の礎を築いた大久保翁の功績については多くの鹿児島県民が認めているところだったが、やはり、「盟友である西郷を見捨てた男」という怨嗟の感情が百年近く経っても残っていたに相違ない。最終的に銅像は建立されたのだが、そういう一部始終を見聞きするにつけても、「薩摩」という存在がこの国に実に大きな痕跡を残したのだということが思い知らされて、小生はますますこの地に魅きつけられるようになった。
おっと、つい寄り道が長くなってしまったが、このたびの話題は、冒頭に触れた「篤姫」である。この物語は実に「薩摩」の物語であった、と思う。篤姫も「薩摩びと」なら、その篤姫が守らんとする徳川を倒しに行くのもまた「薩摩びと」である。ここにこそ、この物語が人の涙腺をして緩ましめる最大の理由がある。番組の最後のほうに出てくる勝と西郷による「江戸城無血開城」は、まさしく世界史に例を見ない「無血革命」であったが、その背景に大きく篤姫の尽力があったというのは間違いのない史実だろう。
その頃、「最後の将軍」たる徳川慶喜は朝廷への恭順の意を示すために既に江戸城を離れ、蟄居している。篤姫は将軍の母として、また、「大奥」の主として西郷に将軍の助命と徳川宗家の存続を切々たる手紙をもって懇願する。西郷にしてみれば、崇拝してやまない島津斉彬が戦略として江戸に送り込んだ娘が篤姫であったのだからして、その要請には心を強く揺さぶられたに違いない。それが「無血開城」につながった。もちろん、戦端が開かれることによって列強の干渉を招く恐れがあるという危機感もあったろう。
いずれにしても篤姫は「江戸」という時代を流血なしに締めくくるために文字通り、心血を注いだ。そして、最後の最後まであくまでも「徳川」の人間として「薩摩」に滅ぼされる道を選ぶ。晩年は相当に困窮したとされているが、それを案じて申し入れた薩摩からの援助も断り、孤高を保った中で朽ち果てていく。しかし、最後の時まで「徳川」を貫いたその篤姫の矜持を成りたたせていた心魂は、「徳川」のものと言うより、むしろ「薩摩」のものであっただろう。
何度も言うとおり、「滅ぼすも薩摩びと、滅ぼされるも薩摩びと」というこの悲哀と相克に観る者は思わずひきずりこまれてしまうのだが、総じて感嘆すべからざるのは、この両方の主役を見事に演じきって新しい時代を幕開けた「薩摩びと」の持つ強烈な使命感と確たる大局観、そして、それらの人物群を育んだ「薩摩」という生命体が有していた大器量である。
それが奈辺から来ているのかについては浅学な小生にはよくわからない。 「風土」や「伝統」などという言葉では簡単に片付かないものであることは容易に想像がつく。「斉彬」や「西郷」や「大久保」といった英傑の存在だけに帰するのも答えにはなるまい。確かなことは、斉彬にしろ、篤姫にしろ、西郷にしろ、大久保にしろ、あるいは小松にしろ、毎日、あの雄大な桜島の景色を眺めつつ「人」となった、ということだ。そして、その人たちが日本を大きく変えた。
誰しもあの桜島の雄姿を仰ぎ見、少しでも薩摩の空気を吸って過ごしたことのある者は皆、「薩摩隼人」である。少なくとも自分は勝手にそう思っている。父もきっとそう思っていただろう。その思いがあるからこそ、「篤姫」には毎回、泣かされた。
しからば、この混迷せる時局において現代の「薩摩隼人」はいったい何を思い、何を為すべきか。この作品を見終えて、自分はそんなことを今考えている。