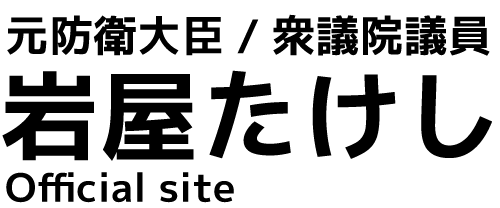忙中閑話「ハットトリック」
そう。これはサッカーの言葉である。「ハットトリック」とは一人の選手が一試合で三得点をあげることをいう。野球で言えば、「一試合三ホームラン」、あるいは「サイクルヒット」というところだろうか。いずれにしてもなかなかできる仕業ではない。サッカーのごとき、点が入りにくいスポーツであれば、なおさらのことである。
しかし、それをやったのである。え、誰がって?Jリーグの話ではない。むろん、まだ始まっていないワールドカップの話でもないからして、中田や小野の話でもない。実はうちの息子の話なのである。そうなのだ。今日は相当に「親馬鹿モード」で書いているのだからして、まぁ、笑って読んでくださればそれでいい。
実はいまをさかのぼること、約一ヶ月。ちょうどゴールデンウィーク中のできごとだった。その日、小生はあいも変わらず、地元行事をせっせとこなしていたのだが、その途中に中学三年生の息子のサッカーの試合があるんだと言って、いそいそと朝から弁当を持って出かけていった家内のことを思い出した。「ちょうど次の会合まで時間が空いたなぁ。。そうだ。たまにはあいつの試合でも観にいってやるか。はて、場所はどこだったっけ?」と思いつくままに家内の携帯に電話をしてサッカー場へ向かうことにしたのである。
息子は市内の中学校のサッカー部に属している。いまどきは「クラブチーム」なるものがあって、Jリーグの下部組織としての少年チームなどがある。本当に上手な選手達はそこに所属しているので、「中体連」などの大会には出てこない。最初から「一軍」と「二軍」に分れているようなもので、そういうのはいかがなものかと思わないではないが、まぁ、そんな時代なのだろう。したがって、わが息子が出ている大会は言ってみれば「二軍」の大会ということになる。だが、小生はそれでいいと思っている。なにもプロを目指すのでないならば、同じ学校に通う仲間たちとひとつのボールを追いかけることこそ、「青春」らしいではないか。
サッカー場に着くと、グラウンドでは既に少年達がひとつのボールを追って熱戦を繰り広げていた。息子は既に自分より背が高い。色も自分に似て黒いからして遠目でもすぐにわかった。応援席はほとんどお母さんたちで占められていて、中にはお父さんの姿もあるものの、小生のように背広ネクタイ姿の人などいないので、どうしても目立ってしまう。「親父が来たっ!」と息子が緊張してもいかぬと思って上着を脱いで手にかけ、見つからないようにと恐る恐るグラウンドのほうへ近づいていき、静かにスタンドのはしっこのほうに席を取って観戦モードに入った。
どうやら、四国からやってきたチームと試合をしているらしい。なんとなく「自軍」のほうが球の回りがいいように見える。しかし、こうして中学生の試合を見ていると懐かしくも切ない思いがこみ上げて来る。実は小生も中学校時代はサッカー部に所属していたのだ。当時はどうしても野球のほうがメジャーなスポーツで、サッカーはどちらかというとまだマイナーだった。まぁ、その頃の我々のあこがれの選手が「釜本」だったり、「杉山」だったりという時代だから、Jリーグのスター軍団花盛りの今から考えるとずいぶんと開きがある。
小生の所属するチームは市内の中学校では一番強かったのである。けれども県大会に行くと、どうしても勝てない宿命のライバルがいて、何度やっても準優勝しかできなかった。まぁ、それでも「大分県で二位」というのは、自分たちにとっては誇らしい記録だった。小生は正直、あまりうまい選手ではなかった。ポジションは当時でいうところの「バックス」。今で言うと「ガード」と言うのだろうか。要するに守備要員である。したがって、得点に絡むようなことはほとんどない。ひたすら、敵の攻撃を体当たりのスライディングなどでカットする役回りだった。
そういうわけで、小生、残念ながら中学校三年間を通じて得点をしたことは一度もない。まてよ、、、いやいや、一点だけあったな。。。それも恥を承知で告白すれば、「自責点」だった。いわゆる「オウンゴール」というやつだ。あぁ、嫌なことを思い出してしまった。今、思い出しても冷や汗が出る。自分にとっては決して忘れることのない屈辱的な思い出だ。
あれはそう、さっき言った「宿命のライバル」との練習試合でのことだった。練習試合といっても県大会本番前のテストマッチだったから、双方、相当に気合いが入った試合だった。このチームはやたらと個人技に秀でた選手が多くて、中盤がいとも簡単にスルスルとドリブルやパスで崩されてしまう。あっという間にゴール前まで迫ってくるのだ。試合の大半を自陣で必死に守備に当たり、たまに相手のミスでボールが取れたら、そこからやっとカウンター攻撃を仕掛けていくことができたという程度の苦しい試合展開だった。
小生も必死になって相手ボールをクリアーするのだったが、敵も俊足ですぐに迫ってくるので、味方チームにパスをつなぐ余裕などなく、ひたすらサイドラインやゴールラインにとりあえず球を蹴り出すしかなかった。するといきおい、相手のフリースローやコーナーキックで再び猛攻にあうことになる。そんな相手の攻撃が絶え間なく続いていた時だった。コーナーから放たれた相手のセンタリングがちょうど自分の頭上めがけて飛んできたのである。
キーパーは大声で「クリアー!クリアー!」と叫ぶ。落下点めがけて相手の最長身の選手が飛び込んできたので、小生も必死にジャンプして大きく頭を振った。「ここはコーナーキックが続いても仕方がない。ゴールラインを割って出そう」と、とっさに判断したのだった。しかし、着地してボールの行方を追おうと後ろを振り返って、ぞっとした。小生の頭をはねたボールはちょうど味方のキーパーの逆をつく形となって自軍のゴールめがけてコロコロと転がっているのである。
思わず目をつむった。その直後に「ピーーッ!」というおぞましい笛の音が響く。あぁ、やってしまった。オウンゴールである。キーパーは呆然。味方も唖然。キーパーは寝そべったまま立ち上がろうともしない。その当時、小生の無二の親友がキャプテンをしていたのだったが、緊迫した状況で出た味方のミスに相当に腹が立ったのだろう。「馬鹿ヤロー!なにやってんだっ!」と今まで聞いたことのない罵声までが彼から飛んできた。「すまん・・・」と言ったが、声が続かない。相手チームは手をたたいて喜んでいる。中には「ナイスシュート!」とあざける奴までいた。全身が真っ赤になり、自分で自分に無性に腹が立ったが、もう、あとの祭りだ。結局、その試合は2対1で敗れたのだったが、あの「自責点」さえなければ、と思うと、それからしばらくの間、まさしく「自責」の念にかられ続けた。。。。。
今になっても時折、夢に出てきてうなされるその時のことを思い出していたら、「岩屋くぅーん、行け行けぇ!」という大声で我にかえった。グラウンドに目をやると息子のチームがこれから相手陣内でコーナーキックに臨むところだった。背の高い息子はこういうときは「ヘディング要員」なのだろう。相手のガードとおしくらまんじゅうをしながら飛んでくる球に備えている。ボールが蹴り上げられた。綺麗な放物線を描いて息子が待つ方向へと飛んでいく。これは絶妙のポジショニングだと予感した。息子がジャンプし、思いっきり頭を振る。その瞬間、「やった!」と確信できた。ボールはキーパーの真横をワンバウンドしてゴールネットをゆらした。「よぉーっしゃ!やったぁ!」。思わずこぶしを突き上げていた。
お母さんたちも大はしゃぎだ。一緒になって歓声をあげている。家内が威張ったふりをして言う。「いまのはうちの息子よ、うちの息子でございまぁーーす!」。もうひとりのお母さんが続ける。「コーナーキックを蹴ったのはうちの息子なのよぉーー。センタリングがよかったからよ。そうでしょぉーー」。むろん、その両方なのだが、ともあれ、無茶苦茶に嬉しい。ベンチに控えている選手が言った。「これで岩屋君は今日、二点目でぇーす。あとひとつでハットトリックです!」。え、なんだって、今のは二点目だって。それは凄いっ!。。。親父は三年間で自責点一点だけだってのに、一試合で二点も入れたのか。。。。これでもう自分には十分に思えた。
しかし、である。試合終了直前にとうとう「快挙」達成のチャンスが訪れたのである。ゴール前で相手のパスミスからボールを奪った息子は今度はドリブルで相手ガードを次々と抜き去った。残るは敵のキーパーひとり。こういうときのフェイントは実に難しい。思わず「行けっ!」と声が出る。食らい突いてくるキーパーを我が息子ながら絶妙なフェイントで振り切った。「よしっ!」。息子は無人のゴールへ向かって余裕をもってゆっくりとボールを蹴りこんだ。「やったぁーー! ハットトリックだ、これは凄いぞぉ!小遣いはずんでやるぞぉー!!!」と、思わず我を忘れて大興奮。前に座っている家内も「今日はおかずいっぱいつけてあげるわよぉーー!」と叫ぶ。いやはや、まさかこんなものを見せてくれるとは思ってもいなかった。
「親馬鹿」の言葉どおり、親というのは本当に馬鹿なもので、日頃は「あいつ、サッカーばっかりやってて大丈夫か? いつも寝ていて勉強できてないようじゃないか。まぁ、そこそこにさせないとな。」などとブツブツ言っていたものが、「ウウム。これならもう少し早く始めさせておけばよかったかな。少しは才能がありそうだ。」などとコロッと気持ちが変わってしまう。最近では野球場でもサッカー場でもステージママならぬグラウンドママやグラウンドパパが大勢たむろしていて、「よくぞまぁ、そこまで熱心になれるものだ」などと内心、あきれていたのだったが、こうしてみるとその気持ちが実によくわかる。
我が息子の快挙に十二分に満足して小生はグラウンドを離れることにした。彼はとうに小生が来ていることに気づいていたようで、こちらを「エヘン!」という誇らしげな顔で見ている。いや、君は実によくやったよ。その「エヘン!」はパパも文句なしに認める。僕は車に向かいながら、息子は中学校を卒業するまであと何得点あげられるだろうか、と思った。でも、ハットトリックなんてことはもう何度もないだろうな。いや、もうこれっきりかもしれない。でも今日のことは彼の記憶の中にきっと「誇り高き思い出」として残っていくだろう。お陰で今日はパパも何十年かぶりに溜飲を下げさせてもらったよ。
ほどなくドイツの地で展開される「サムライ・ジャパン」の活躍も、君のハットトリックほどにはパパの胸を熱くはしないだろう。これからの人生に何度か「自責点」はあるだろう。でも、大事なことはまっすぐ前に向かっていたかどうか、そのあともその屈辱を乗り越えてもっと力強く前に進めたかどうか、だと思う。「そうだ。もう、あの自責点のことは忘れよう。」 あの日、僕はそう心に決めてサッカー場をあとにした。