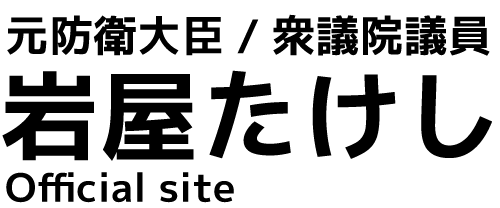忙中閑話「父の思い出」
父は59歳で逝った。
自分が45歳になってみると、なんと早く逝ってしまったことかと思う。父が亡くなったのは最初の衆議院選の最中だった。当時は「中選挙区」時代で、同じ自民党の先輩議員がライバルである。公認も取れず、無所属での立候補。当然、集会をやっても人は集まらない。仕方なく宣伝カーを仕立てて、勝手にあらゆる集落に乗り込んでいって、街頭演説をすることが主な運動方法だった。
選挙戦初日、出陣式を終えてタスキをかけたまま、父の入院している病院へと急いだ。医者からは「選挙が始まるまでもつかどうか」と言われていただけに、せめて戦いが始まったということだけは父に知らせたかった。既にベッドの上でチューブだらけになっていた父はタスキをかけた自分の姿を横たわったままじっと見つめた。父はもはや言葉を発することはできなかったが、「がんばれよ!」という声が聞こえたような気がした。
選挙が始まって一週間たったその日の朝、父は力尽きたように静かに逝った。ガンであることの「告知」はしていなかったが、医師であった父には自分の病状はわかっていた。そのことを了解して以降は、一度も「痛い」とも「苦しい」とも誰にも言わなかったという。立派な最後だったと思う。選挙戦の真っ最中に行なわれた父の葬儀は事実上、選挙戦での最大の「集会」となった。弔いに行くのに誰憚ることはない。父の有縁の方々はもちろん、隠れていた私の支援者が一挙に集結し、さながら気勢を上げない「決起集会」となった。

私には今でも父が死ぬ時を選んで逝ったとしか思われない。初陣を飾ることができたのは、父が自らの命と引き換えに自分の背中を強く押してくれたからだ。そういう意味で父は最後まで「政治家」であったと思う。病床にあって思うように加勢ができない自分にできることは何か、と終始考えつづけてくれていたに違いない。そして、もっとも意味がある時を選んで父は逝った。
とても人懐っこくお茶目な人だった。交友関係も広く、よく人の面倒もみた。医者で県議というと、お偉いさんばかりが周りを取り囲んでいたように思われがちだが、父はむしろ、そうではない人たちとの交流を好んだ。子どもの頃、実に様々な人々が我が家を出入りするのを目をシロクロさせながら見ていたことを思い出す。一言で言えば人がよかった。それゆえにしばしば人に騙されたりもしたようだが、だからといって文句を言うようなことはなかった。今でも「アンタはよく知らないが、お父さんには大変世話になった。だから応援するんだ」と思わぬ人から声をかけられたりする。そういう意味では、いまだに父から背中を押しつづけてもらっている。
いま、自分も三人の子の父親となった。事あるごとに、さて、子どもに何と言おうか、と迷うことしばしばである。そんな時は部屋に飾ってある父の写真を見上げて「親父からはどう言われていたっけ?」と考えてみるが、「挨拶をきちんとしろ!毎日、腕立て伏せをやれ!」というのしか思い浮かばない。それよりも、時折、黙ってお小遣いを自分の手に握らせてくれた時の嬉しかったことを懐かしく思い出したりする。親父というのはそんなことでいいのかもしれない。やがて子どもの背中をそっと押してやることができさえすれば・・・・・。